研修内容
オーストラリアの高齢者ケアシステムについて
①ホーンズビークーリンガイ病院―この地区におけるHACCのサービスについて
地域ケア-HACCの予算で提供されるサービスについて
①配食サービス-Meal On Wheels の配達拠点場所を訪問し、話を聞く
②ホームヘルプサービス-ホームヘルプサービスのホーンズビー支部をおとずれ、話を聞く
③訪問看護サービス -スタッフより話を聞く
④コミュニティーオプション プログラム(ケアマネージメント)-マーシーライフセンター訪問
⑤コミュニティー高齢者ケアパッケージプログラム
⑥高齢者ケア評価チームについての話
施設ケア-非営利団体(NPO)が提供している施設を訪問
①リタイヤメントビレッジ
②ホステル
③ナーシングホーム
その他の非営利団体(NPO)
①アルツハイマー協会NSW州本部訪問
② 介護者協会訪問
| 日数 | 月日 | 都市 | 交通機関 | 適用 | 食事 |
| 1 | 11/25(土) | 関空発 | AN又はJL | 機内泊 | 機内 |
| 2 | 11/26(日) | シドニー着 | 専用車 | 到着後ホテルへ シドニー箔 |
機内 |
| 3 | 11/27(月) | シドニー | 専用車 | モハンドビレッジ視察訪問 シドニー箔 |
朝昼夜 |
| 4 | 11/28(火) | シドニー | 専用車 | レタイヤモントビレッジ視察訪問 シドニー箔 |
朝昼夜 |
| 5 | 11/29(水) | シドニー | 専用車 | アルツハイマー協会本部訪問 シドニー箔 |
朝昼夜 |
| 6 | 11/30(木) | ブリスベン | 専用車 | 介護者協会・高齢者ケア評価システム 視察訪問 |
朝昼夜 |
| 7 | 12/1 (金) | ブリスベン | 専用車 | ゴールドコーストなど観光 | 朝 |
| 8 | 12/2 (土) | シドニー発 関空着 |
AN又はJL | 専用車で空港へ 到着後解散 |
朝 |

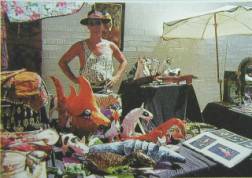
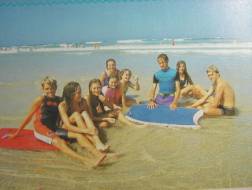
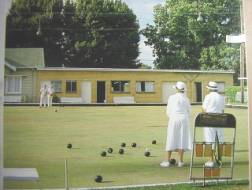

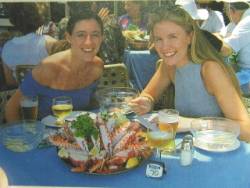
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
| 日時 | 平成12年11月27日(日) | 平成12年11月28日(火) | 平成12年11月29日(水) | ||
| 場所 | ホーンズビー クーリンガイ病院 |
マーシーライフファミリー センターNSW州アルツハイ マー協会 |
ハモンドビレッジ | ||
| 通訳 | トーマスフィッツギボン氏 | トーマスフィッツギボン氏 | トーマスフィッツギボン氏 | ||
| 0800 | ホテル出発 | 0800 | ホテル出発 | 0800 | ホテル出発 |
| 0900 | 歓迎のご挨拶、はじめに | 0900 | 歓迎のご挨拶、はじめに | 0900 | 歓迎のご挨拶、はじめに |
| オーストラリアの保険医療制度 | 非営利団体であるマーシーファミリーセンターの活動について | オーストラリアの痴呆症ケアの歴史 | |||
| オーストラリアの高齢者ケア | マーシーライフファミリーセンターが提供している痴呆症高齢者のための地域ケアについて | オーストラリアで成功している痴呆症 ケアモデルの不可欠要素 |
|||
| 高齢者評価チームについて | マーシーファミリーセンター内の施設見学 | 昼食 | |||
| 配食サービスの拠点地訪問 | 昼食 | 痴呆症高齢者専門施設訪問 | |||
| 器具の貸し出し部門見学 | NSW州アルツハイマー協会へ 移動 |
デイケアセンター見学 | |||
| 昼食 | NSW州アルツハイマー協会の 活動について |
質疑応答 | |||
| ホームヘルプサービスについての説明 | NSW州アルツハイマー協会の 見学 |
||||
| 訪問看護についての説明 | 質疑応答 | ||||
| リチャードジーブスデイケア センター訪問 |
オーストラリアの老人医療 関根光男(内科医)
老人の医療・福祉については福祉先進国である北欧諸国に学ぶべきことは多いが、その徹底したシステムと税率の高さを考えると、日本のモデルとするには高嶺の花といった感じがしないでもない。オーストラリアの国民一人当たりの医療費と国民所得との関係および老人比率は世界的にみて日本にもっとも近いことから、オーストラリアのシステムは老人医療・福祉後進国の日本でも、医療費の配分方法を改革すれば財政的には到達不可能ではなく中期目標としては最適ではないかと思われる。筆者はオーストラリアでの虚弱老人に対する保健・医療・福祉の総合システムを学ぶため、シドニー郊外の州立病院(ホーンズビー・クーリンガイ病院)を中心とした1年間の研修を行った。本稿ではその経験からオーストラリアの老人医療・福祉の概略を述べてみたい。
施設収容から地域ケアへの転換
オーストラリアの虚弱老人に対するケアは、1985年に在宅地域ケア事業、HACC(Home
and Community Care Program)が施行されてから、施設収容から地域でのケアへと、ダイナミックな政策転換が行われた。虚弱老人は可能なかぎり住み慣れた地域で生活することがQOLの向上につながる。そのための地域での支援体制を法的に保証し、不必要な施設入所をなくす、というのが主旨である。
必然的にナーシングホームに対する巨額の補助金の削減にもつながり、まさに一石二鳥の政策転換となった。
オーストラリアで老人医療の中核となっているのは州立病院の老人・リハビリ病棟である。オーストラリア全体の病院の平均在院日数は6日と世界で一番短いが、ホーンズビークーリンガイ病院の老人・リハビリ病棟(平均年齢80才)の平均在院日数は20日である。退院した患者の転帰先は入院前の居住場所が67%であり、半年以内の再入院率は20%である。また再入院の原因が前回と同一例は21%で、再入院後の転帰、平均在院日数は前回の入院と比べて有意差はない、したがって患者にとって早すぎる退院ではないといえよう。
こうした平均在院日数の短縮は、HACCの諸サービス、およびナーシングホーム・ホステルなどの施設と病院との入院時からの緊密な連携によることが多い。人口22万人のホーンズビー・クーリンガイ地域での老人の保健・医療・福祉サービスは図1のようにバラエティーに富んでいる。各サービスの代表者の連絡会議はユーザー代表も含めて月1回定期的に開かれており、活発な意見交換がなされている。大腿骨頚部骨折の患者についていえば平均在院日数がHACC施行前と比べて約2割短縮されたのは注目に値する。
マンパワーの問題点
早期退院を実現するためにもっとも重要な役割を占めるのはマンパワーであるが、単位人口当りの医療職の数を比較すると、オーストラリアと日本とのマンパワーの差は歴然としてくる。オーストラリアを100とすると、日本は80、ナース57、PT27、OT12となり、21世紀の高齢社会に対応するには特にナース、PT、OTの圧倒的な少なさが目立つ。
オーストラリアでは現状のマンパワーでも十分ではなく、病院には多数のボランティアが協力している。また各施設の専門性が強化されているだけでなく、その専門性を施設内に限定せず地域へと広げていることは今後の日本の方向性を示唆している。
モデル地域へのヒント
世界一の長寿国日本において、いま問われているのは長寿の質である。しかもその高齢化のスピードから考えて、すでにいくつかのモデル地域ができていなければ、今後の高齢社会には対応できないところまできている。利用者のニーズに応じたオーストラリアの保健・医療・福祉の統合システムは、日本にとっても実現可能な多くのヒントを与えてくれる。
キーワード:保健・医療・福祉の統合 在宅地域ケア事業 HACC
平均在院日数
(医学のあゆみ VOL.161 No.4 1992.4.25
せきね みつお)